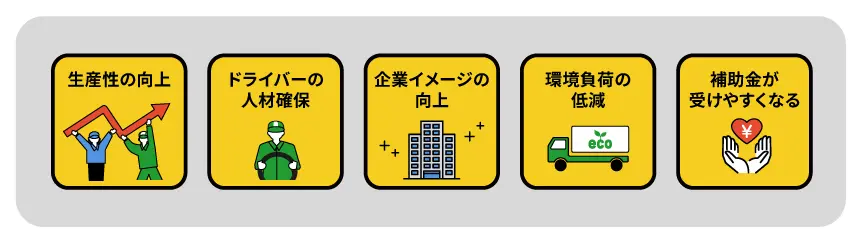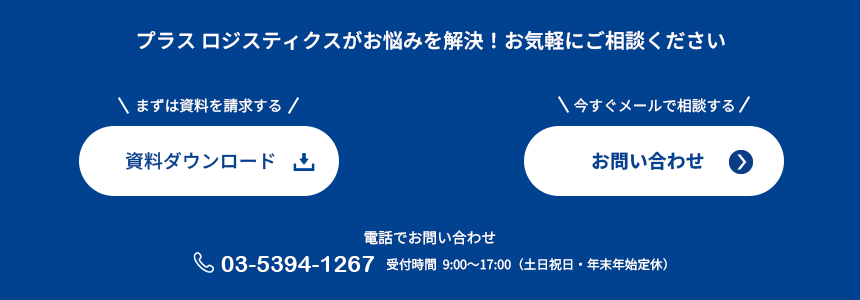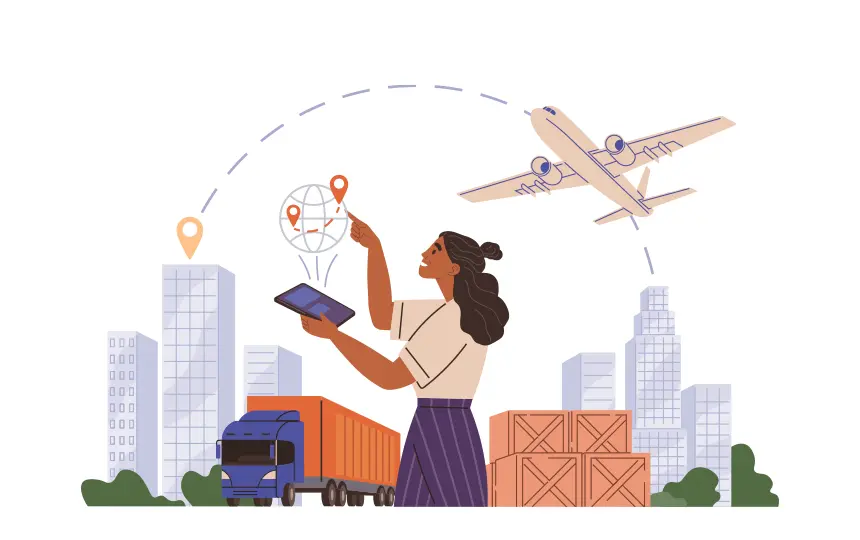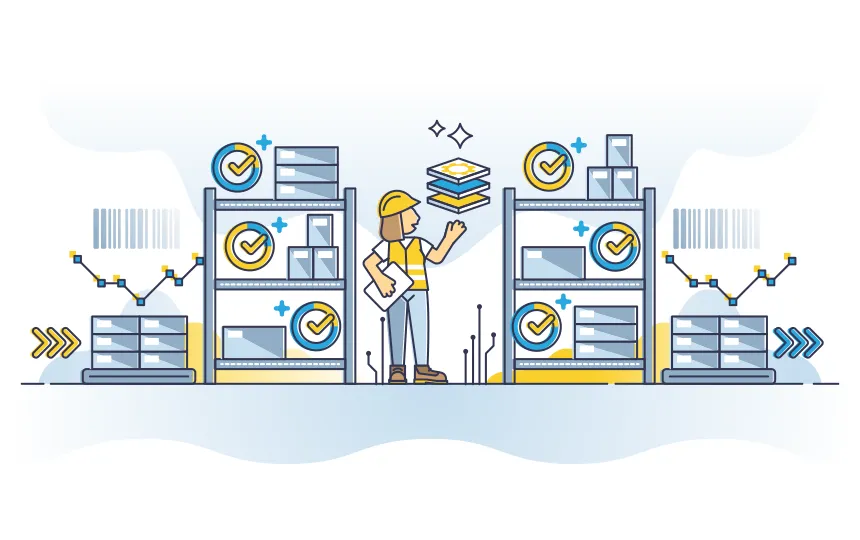この記事は、 11 分で読めます。
国が推進する「ホワイト物流」とは、トラック輸送の効率化とドライバーの労働環境改善を目指す画期的な取り組みです。物流業界では深刻なドライバー不足や長時間労働といった課題が表面化しており、これらを解消するために持続可能な物流体制の構築が求められています。
この記事では、ホワイト物流の概要と、なぜ国が推奨しているのか、そして実際に導入することで企業やエンドユーザーにどのようなメリットがあるのかについて、わかりやすく解説します。
ホワイト物流とは物流の効率化と労働環境の改善を目指す施策
物流業界では、トラック運転者や物流倉庫内スタッフの高齢化や人手不足、長時間労働などが深刻な課題となっています。これに対し、国が推進しているのが「ホワイト物流」です。ホワイト物流とは、物流の効率化とドライバーの働きやすさを両立させ、持続可能な物流体制を実現するための施策をいいます。
この施策は、「トラック輸送の生産性の向上・物流の効率化」と「女性や高齢者を含む誰もが働きやすい、よりホワイトな労働環境の実現」という2つの柱を掲げています。単なる労働条件の見直しにとどまらず、業務プロセス全体の見直しや、荷主企業との連携強化などが求められています。
2025年3月現在、3,140社以上の企業がこの運動に賛同しており、その数は年々増加傾向にあります。国土交通省、経済産業省、農林水産省の3省が共同で推進しており、企業のホワイト物流への取り組みを後押しする各種支援策も充実しています。
※参考 「ホワイト物流」推進運動事務局「『ホワイト物流推進運動』ポータルサイト」
国が「ホワイト物流」を推奨する理由
国がホワイト物流を強く推奨しているのは、物流業界の構造的な課題が深刻化しており、対策が急務だからです。特に「人手不足」「物流の安定的な確保」「経済成長への影響」という3つの観点から、ホワイト物流の推進は不可欠とされています。この3つの観点について、下記で詳しく解説します。
人手不足の解消
現在、物流業界では慢性的なドライバーや物流倉庫内スタッフの人手不足が続いており、高齢化と若手の人材難が重なって、今後さらに深刻化が見込まれています。そこで、ホワイト物流では、荷待ち時間の削減や業務負担の軽減など、働き方の見直しを通じて労働環境を改善し、運転者や倉庫内スタッフの確保と定着につなげようとしています。
国民生活や産業活動に必要な物流の安定的確保
物流は日々の生活や産業活動を支えるインフラのひとつです。物流が滞ると、物資の流通に支障をきたし、国民生活や企業活動に大きな影響を及ぼします。ホワイト物流の推進により、サプライチェーン全体の効率化を図り、物流の安定供給を維持することが重要とされています。
経済成長への寄与
物流の停滞は経済の停滞に直結します。一方で、物流の効率化が進めば、企業活動の円滑化、コスト削減、生産性向上といった好循環が生まれ、結果的に経済成長に寄与します。ホワイト物流は、持続的な経済成長を支える基盤のひとつとしても注目されています。
ホワイト物流導入のメリット
ホワイト物流を導入することで、物流事業者だけでなく荷主企業にもさまざまなメリットがあります。単なる労働環境の改善にとどまらず、企業経営全体の効率化や社会的評価の向上など、多方面にポジティブな影響をもたらします。企業がホワイト物流を導入するメリットは、下記のとおりです。
■ホワイト物流を導入するメリット
生産性の向上
物流のムダを見直し、配送ルートや業務フローを最適化することで、生産性が大きく向上します。例えば、荷待ち時間の削減や積載効率の改善は、運行回数の最適化にもつながり、全体のコスト削減にも寄与します。
ドライバーの人材確保
ホワイト物流の推進により、長時間労働の是正や荷待ち・荷役時間の短縮が実現すれば、ドライバーの労働条件が改善されます。これにより、ドライバーの離職防止や新規人材の採用がしやすくなり、慢性的な人手不足の解消が期待されるでしょう。
企業イメージの向上
ホワイト物流に賛同し、積極的に取り組む企業は、「『ホワイト物流推進運動』ポータルサイト」などで公表されます。これにより、取引先や消費者からの信頼性が向上し、企業ブランディングへの効果も期待できます。さらに、物流の安定供給が企業活動全体の信頼性向上につながるでしょう。
環境負荷の低減
輸配送の効率化によってトラックの走行距離や台数を削減でき、CO₂排出量の低減にも貢献します。環境に配慮している企業として評価されることで、SDGs対応やCSR活動の一環としてもプラスに働くでしょう。
補助金が受けやすくなる
ホワイト物流推進運動への賛同は、国や自治体が実施する補助金制度の審査で評価されることがあります。単に賛同するだけでなく、実際に改善策を実行することが求められますが、それが補助金獲得のチャンスにつながるでしょう。
荷主企業が取り組むべき具体的施策
ホワイト物流の実現には、物流事業者だけでなく荷主企業の主体的な取り組みが不可欠です。荷主企業が物流現場に配慮した改善策を講じることで、ドライバーの負担軽減や効率化につながり、業界全体のサステナビリティに貢献します。荷主企業が取り組める、具体的な施策は下記のとおりです。
予約受付システムの導入
荷主が予約受付システムを導入すれば、トラックの待機時間を削減できるでしょう。ドライバーの拘束時間が短くなり、ほかの配送業務へのスムーズな移行が可能になるため、業務全体の効率化につながります。
入出荷情報などを事前提供する
配送スケジュールや荷物の内容を事前に共有することで、ドライバーや物流倉庫内スタッフの作業の見通しがつきやすくなり、現場での混乱や確認作業の手間が減ります。結果として、作業時間の短縮と安全性の向上が実現できます。
荷役作業の負担を軽減する
パレットやマテハンを活用することで、荷役作業の自動化・省力化が進み、ドライバーや物流倉庫内スタッフの身体的負担を軽減できます。女性や高齢者も働きやすくなる環境づくりにも寄与するでしょう。
生産・出荷工程を見直す
物流の混乱を引き起こす原因のひとつは、突発的な出荷や非効率なスケジュールです。全体の工程を見直し、計画的な出荷体制を整えることで、物流業務がスムーズになり、無駄な労力や時間の削減が期待されます。3PL(サードパーティ・ロジスティクス)の活用も有効です。
卸し先を集約する配車を見直す
配送先を集約した効率的なルートを設計することで、移動距離の短縮や積載効率の向上が実現します。これにより、トラックの稼働回数を減らし、コストと環境負荷の両方を削減できるかもしれません。
物流事業者が取り組むべき具体的施策
ホワイト物流の実現には、実際に物流を担う物流事業者側の取り組みも重要です。特にテクノロジーの導入や業務プロセスの見直しによって、効率化と働きやすさを同時に追求することが求められます。物流事業者が取り組むべき具体策は、次のとおりです。
配送ルートを最適化する
AIを活用した配車システムやルート最適化ツールを導入することで、無駄な走行や待機時間を削減できます。これにより、ドライバーの拘束時間が短縮されるだけでなく、燃料費の削減やCO₂排出量の削減といった効果も期待できるでしょう。
プラス ロジスティクスが物流を請け負っている産業機械の専門商社の中部センターでは、Loogia配送システムを導入し、毎日の配送ルートを最適化しているほか、積載率が10%向上し、自社便の配送個口数が月間で15%拡大するなど多くの成果を上げています。
配送ルートの最適化について、詳しくはこちらを参考にしてください。
車両管理システムの導入
GPSやIoTを活用した車両管理システムを導入すれば、運行状況の可視化やスケジュール管理が容易になります。遅延リスクの低減や安全運転の促進が実現し、顧客満足度の向上にもつながります。
ドライバーの負担を削減する
ドライバーの負担を軽減するには、荷受けや荷役作業に関する運用方法の見直しが必要です。例えば、受け取り体制の改善や荷下ろしのサポート体制を整えることで、作業効率が大きく向上します。さらに、女性や高齢者が無理なく働ける環境整備も、今後の人材確保において欠かせません。
プラス ロジスティクスグループで輸配送を担っているプラス カーゴサービスでは、東日本エリアで約320店舗を展開する大手小売チェーン店への配送業務を請け負っており、配送仕分け時の業務効率化のため、独自の配送トラッキング検品システムを開発・導入しています。ドライバーが荷物積込時にかかる時間を約50%削減し、負担軽減につながっています。
配送トラッキング検品システムについて、詳しくはこちらを参考にしてください。
荷主企業と物流事業者が連携すべき具体策
ホワイト物流の成功には、荷主企業と物流事業者の連携が必要です。いずれかによる一方的な改善では限界があるため、双方が協力し合い、課題を共有しながら業務改善に取り組む必要があります。荷主企業と物流企業が連携して取り組むべき具体策は、次のとおりです。
物流を改善し、事業者同士が協力する
従来の物流のやり方を互いに見直し、生産性向上に向けた協力体制を築くことが大切です。例えば、鉄道や船舶へのモーダルシフトを検討したり、配送料金体系を見直したりすることで、物流の持続可能性を高めることができるでしょう。
人的工数の最適化を図る
ドライバーや物流倉庫内スタッフの労働負担を軽減するためには、荷役作業の工数そのものを減らす工夫が必要です。パレットやロールボックス、折り畳みコンテナなどの標準化・共有化を推進することで、作業時間の短縮と人員の効率的配置が可能になります。
輸配送以外の物流全体の最適化を図る
荷待ち時間や積み込み作業の効率化、リードタイムの見直しなど、輸配送にとどまらない物流プロセス全体の最適化も重要です。荷主企業と物流企業の双方で課題を共有し、改善案を出し合うことで、ドライバーの拘束時間削減と業務全体のスムーズ化が実現できます。
エンドユーザーである国民にもホワイト物流の理解を促している
ホワイト物流の推進は、荷主企業と物流企業といった企業や行政だけでなく、エンドユーザーである国民一人ひとりの理解と協力も重要です。物流を支えるドライバーの負担を軽減し、持続可能な体制を築くためには、エンドユーザー側の意識変革も求められています。
具体的には、再配達の削減や引っ越し時期の分散、即日配達から置き配への変更といった行動が挙げられます。こうした取り組みにより、物流現場の過重な負担を減らすことが可能です。
さらに、物流を利用する際にはホワイト物流に取り組む企業を選び、応援するといった消費行動も、企業のモチベーション向上に寄与します。国民の理解と協力が広がることで、ホワイト物流の取り組みが社会全体へと定着していくといえるでしょう。
物流業務の効率化でホワイト物流を実現してみませんか?
ホワイト物流は、単なる業界の改善施策にとどまらず、持続可能な社会や経済成長に貢献する重要な取り組みです。荷主企業・物流事業者・消費者の三者が連携し、それぞれの立場でできることから始めることが、今後の物流の未来を左右します。
物流専門企業であるプラス ロジスティクスでは、物流業務の効率化に向けた改善提案や倉庫運用の受託などを通じて、ホワイト物流の実現を支援しています。これからの物流に求められるのは、システム・仕組みによる効率化です。新しい物流の形を作りたいと考えている荷主企業様は、ぜひご連絡ください。物流のプロならではの提案力で、従来にはない物流を形にします。