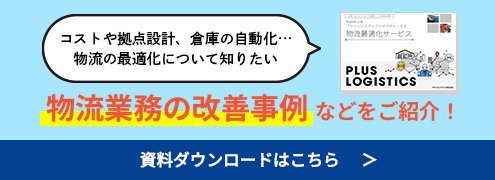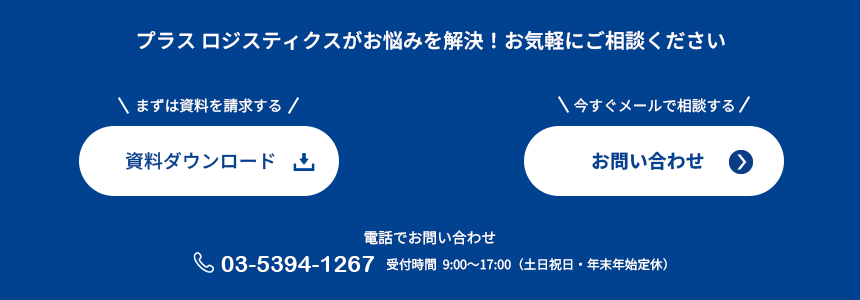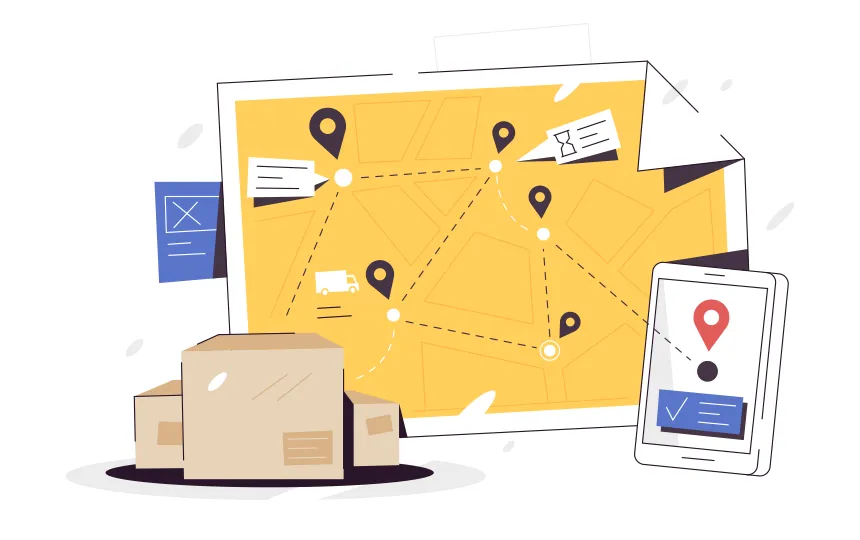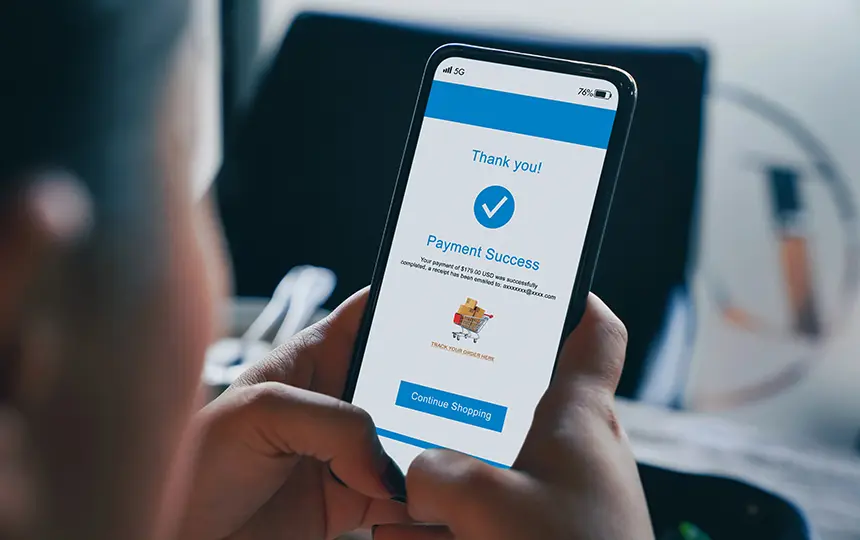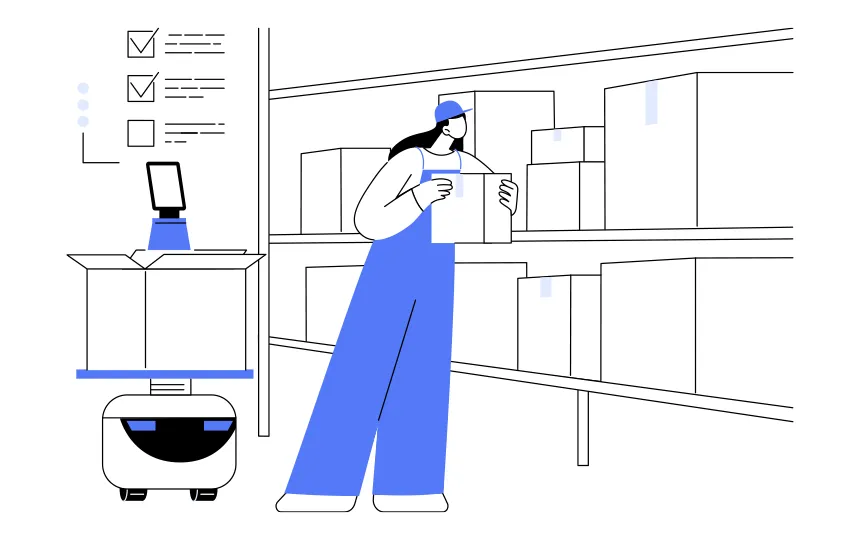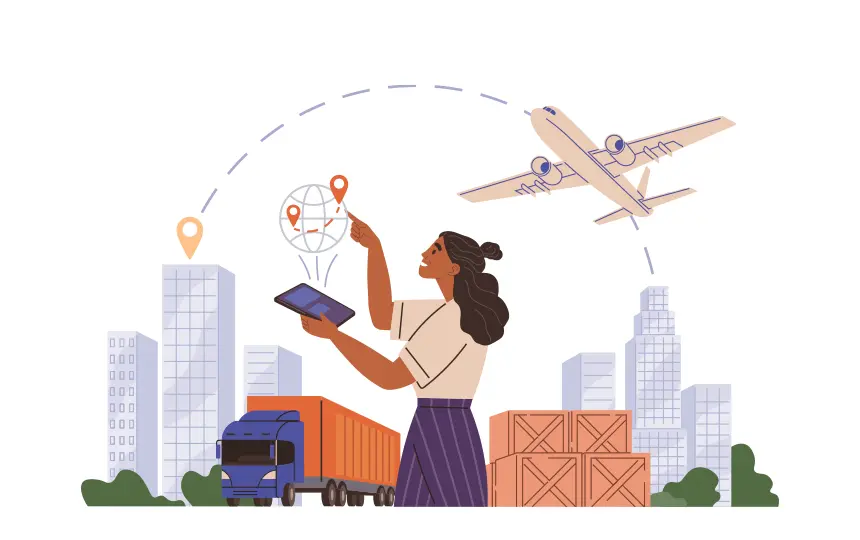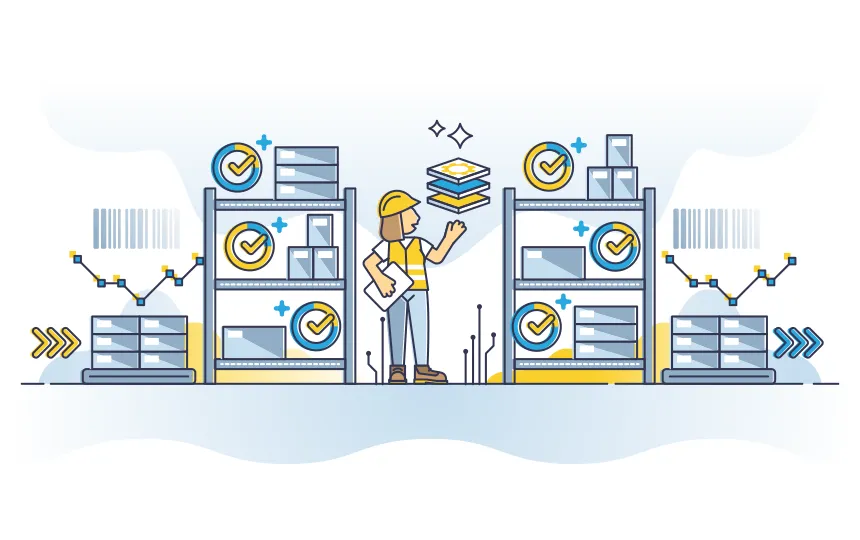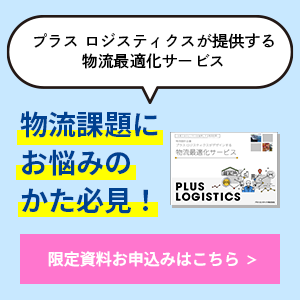この記事は、 12 分で読めます。
入庫とは、物流倉庫や物流センターの棚などに商品や資材を格納する業務のことです。商品を載せたトラックが倉庫などに到着すると、いくつかの業務を経て、入庫することになります。入庫した段階で、商品の数を在庫数に反映させます。受注後に商品を探し出すピッキング業務にもつながるため、正確性が求められる重要な業務といえるでしょう。
この記事では、入庫業務の基本的な内容のほか、その後の物流の品質を左右する入庫業務の重要性と効率化のポイントを解説します。
入庫とは商品や荷物を、物流倉庫や物流センターの棚などに格納すること
入庫とは、商品や荷物や資材を、物流倉庫や物流センターの棚やラックなどの場所(ロケーション)に保管する業務のことです。「棚入れ」と呼ばれる場合もあります。受け入れた商品をあらかじめ決められた適切な場所に、スピーディーに収容することが必要です。
物流では在庫数の正確な把握が重要で、入庫した段階で記録していきます。近年は、在庫管理システムを使用することも多いでしょう。
入庫の重要性
入庫業務は、物流全体の中でも重要なプロセスといえます。例えば、倉庫内で誤った場所に商品を格納してしまうと、ピッキング時のミスにつながり、誤配送の原因に。
また、在庫数を正確に記録しないと、在庫数が足りなくなっていることに気づくことができず、受注してもすぐに配送できずに、失注してしまうという事態を招いてしまいます。物流の工程に大きく影響し、ひいてはエンドユーザーからの信頼にも大きく響く入庫業務は、特に正確性が求められるといえます。
入庫と入荷との違い
入庫と混同されがちで、似ている言葉である「入荷」。しかし、入庫と入荷は、意味する業務の範囲が異なります。
入荷は物流倉庫に到着したトラックなどから商品を受け入れる荷受けから、その内容を確かめる検品を経て、棚などに格納する入庫までの一連の作業のこと。つまり、入庫は入荷業務の一部なのです。
物流業務において入荷と入庫の言葉を間違えて覚えてしまうと、業務上のトラブルにつながりかねないので、正しい意味を把握するようにしましょう。
入荷についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
入庫業務の範囲と流れ
続いては、入庫業務の具体的な内容や範囲、業務の流れについて解説します。倉庫内で行われる入庫業務は、大きく分けて下記の2つです。
倉庫へ棚入れをする
棚入れとは、入荷検品後、商品を倉庫内の棚など決められた場所へ運び、格納することです。商品の重さ、サイズなどの属性を考慮し、適切なロケーションをあらかじめ検討しておき、配置します。
受注するまで、商品はこの場所で保管されることになりますが、受注後のピッキングや先入れ先出しを考慮し、取り出しやすさも検討することが必要です。また、倉庫内は整理整頓をし、どこに何があるかを誰が見てもわかるように管理します。
先入れ先出しについてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
在庫情報を記録する
決められたロケーションに商品を格納できたら、在庫情報を記録します。在庫管理表やシステムにその商品の商品番号やロット番号、入荷日などのデータを正確に記録します。
在庫管理表に記入する主なデータは下記のとおりです。
- 商品名
- 商品番号
- 入庫日
- 入庫数
- 在庫数
入庫で生じやすいミス
入庫作業は、商品の受け入れ時に行われる非常に重要なプロセスのひとつです。ここでのミスは、在庫管理全体に影響を及ぼし、後々の出荷や在庫確認に支障をきたすおそれがあります。ここからは、入庫時に発生しがちなミスを取り上げ、その原因と対策について解説します。
商品数のカウントミス
入庫時に生じがちなミスの1つが、商品のカウントミスです。特に大量の商品が一度に入庫される場合、手作業でのカウントは数え間違いが発生しやすくなります。商品数の誤認は、在庫数が実際の数と合わなくなる原因となり、後の出荷や在庫確認で大きな問題を引き起こす可能性があります。このミスを防ぐためには、ハンディーターミナルや自動計数システムを導入し、正確なカウントをリアルタイムで確認できる仕組みが必要です。
データを誤って入力
入庫作業において、商品の数量や型番などをシステムに入力する際に誤ったデータを入力するミスも発生します。誤入力が発生すると、在庫情報が実際の在庫と食い違い、後々の出庫や棚卸の際に大きな混乱を招きます。この問題を防ぐには、入力作業をできる限り自動化し、バーコードスキャナーやRFIDを用いて正確なデータを即座にシステムに反映させることが重要です。ダブルチェックの導入も効果が期待できます。
保管場所の間違い
入庫時に商品を誤った保管場所に配置してしまうミスも、物流現場ではよく見られます。これにより、後のピッキング作業や出庫時に商品が見つからない、あるいは見つけるのに時間がかかるなどのトラブルが発生します。保管場所の間違いを防ぐためには、ロケーション管理システムを活用し、商品を特定の場所に振り分け、データと紐づける仕組みを整えることが有効です。また、保管場所を視覚的にわかりやすく整理整頓することも徹底しましょう。
間違った商品の見落としによる誤入庫
入庫時には、間違った商品が混ざってしまうことがあり、見落とすと誤入庫につながります。誤入庫が起きると、在庫数や品目情報が正確に反映されず、出庫時や棚卸の際に誤差が生じる原因となります。この問題を防ぐためには、入庫時のチェックを徹底し、バーコードやシステムを利用して商品情報と実際の商品の状況を照合することが必要です。また、ダブルチェックの体制を整えることで、ミスの発見率を高めることができます。
入庫業務を効率化するポイント
入庫は前述のとおり、物流業務の中でも重要なプロセスです。入庫を効率化すれば、正しい在庫管理につながり、すべての物流工程の正確性が向上。結果的に、発注元であるエンドユーザーから高い評価を得られるようになり、良好な取引を積み重ねれば、業績の向上が期待できるでしょう。
入庫業務を効率化するポイントは、主に下記の6つがあります。
- 倉庫の整理整頓し、作業マニュアルを作成する
大切な商品を保管する倉庫内は、常に整理整頓し、清潔を保っていることが基本です。商品を清潔に保管でき、破損や汚れを防ぐことができます。どこに何があるかがわかるように整頓されていれば、ピッキング時のミスもなくなるでしょう。
また、入庫の際のルールを設定することで、作業が容易になったり、誤った在庫管理がもたらすリスクも軽減されたりします。いつ、誰が行っても作業の質が変わらないように、作業マニュアルを作成することも大切です。
- ロケーション管理を徹底する
ロケーションとは、商品を入庫する棚や場所のこと。商品の特徴を捉え、倉庫内の動線を踏まえてロケーションを最適化することが、ミスの減少につながります。
例えば、「発注が多く回転率が高い商品は手前に置く」「別の商品にさわらずに取り出せるように配置する」といった工夫が必要です。
- フリーロケーションを活用する
フリーロケーションとは、倉庫内の空いている場所に商品を保管すること。反対に、倉庫内の決まった場所に保管することを固定ロケーションといいます。
期間限定商品や一時的に人気が急増したイレギュラーな商品の入庫にあてられるよう、通常の棚に入らない商品を保管できるフリーロケーションをあらかじめ作っておくことが大切です。倉庫内を整理し、フリーロケーションを常に作っておくことで、急な商品の入庫の際も空いている棚を探す必要がなくなります。必要がなくなれば、またその場所をフリーロケーションにすればいいでしょう。
- 産業用ロボットを導入する
産業用ロボットとは、入荷から入庫までの作業を自動で行うことができるロボットのこと。アーム型の産業ロボット、自動搬送ロボットなどが保管場所まで商品を搬送してくれるというものです。
最新のシステムを導入している倉庫では、大量の商品を扱う際にロボットを活用する事例も増えてきています。産業用ロボットを導入するにはコストが必要ですが、その後の人件費を抑制でき、作業の正確性の向上も期待できます。
- WMSを活用する
WMSとは、在庫の管理や人的リソース、設備管理などを一括管理できる倉庫管理システムのこと。WMSを使えば、ハンディーターミナルを使った入庫管理が可能です。どの商品がどの棚に何個あるかがすぐにわかります。
バーコードを読み取ることで、品番や在庫数を登録できるので、効率的な入庫作業ができるでしょう。
WMS(倉庫管理システム)についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
- 3PLを導入し、アウトソーシングする
3PL(サードパーティロジスティクス)とは、物流の専門業者へ、一連の物流業務を一括アウトソーシングすることをいいます。3PLを導入することで、自社の物流に関わることをすべて外部企業に委託でき、スピーディーで確実な物流が実現可能です。
プラス ロジスティクスグループをはじめとする3PLを請負う物流専門業者は、最新のシステムを活用する物流業務のプロなので、導入することでリードタイムの適正化と、さまざまな管理費の抑制につながります。
入庫作業をアウトソーシングするメリット
入庫作業は物流の重要なプロセスですが、社内ですべてを管理することは、コスト面や業務効率の観点から難しい場合もあります。そこで、入庫作業をアウトソーシングすることにより、業務の負担を軽減しつつ、より効率的な運営が可能です。ここからは、入庫作業を外部委託することで得られる主なメリットについて解説します。
コストを適正化できる
入庫作業をアウトソーシングするメリットは、コストを適正化できることです。自社で従業員を雇用して管理する場合、固定的な人件費や設備投資が必要ですが、アウトソーシングによりそれらのコストを変動費に変えられます。繁忙期や閑散期に応じて外部業者を柔軟に活用できるため、必要な作業量に応じた費用調整も可能となります。また、専門業者が効率的に作業を進めることで、全体的な運用コストも下げられるかもしれません。
生産性が向上する
入庫作業をアウトソーシングすると、生産性が向上することも大きなメリットです。専門の物流業者が効率的かつ正確に作業を進めるため、物流にかけていたリソースをコア業務に集中させることができ、全社的な業績アップにもつながるでしょう。アウトソーシングでは物流専門のスタッフが最新の技術や設備を駆使して作業にあたることで、入庫のスピードや正確性が高まり、全体的な業務効率が期待できます。
物流品質・顧客満足度がアップする
専門の物流業者に入庫作業を委託することで、物流の品質が向上し、結果的に顧客満足度もアップします。物流専門業者の品質管理の精度は高く、誤入庫やミスを減らせるため、正確で迅速な入庫作業が実現されます。これにより、在庫管理がスムーズに行われ、顧客への迅速な対応が可能となり、リードタイムの短縮や品質の向上を実感できるでしょう。
プラス ロジスティクスが改善した2つの入庫作業の事例
プラス ロジスティクスは、荷主企業さまの要望に合わせた入庫作業を実施し、包括的な物流改善に取り組んでいます。ここからは、プラス ロジスティクスが効率化に成功した入庫改善事例として2つの案件を紹介します。
入庫作業を最新システムで簡略化し、物流プロセスを改善
プラス ロジスティクスでは、産業機器、工業機械、住設・管材・空調など幅広い分野の商品を扱うユアサ商事株式会社様の東日本物流センターの運用を一括受託しています。このセンターでは共同開発したピッキング用自動搬送システム「ツインピック」を本格稼働させ、入庫作業も自動で実施。取り扱いアイテム50,000点以上という膨大な数の商品のうち、サイズや重さの条件が合致した約20,000アイテムの入庫作業のほか、ピッキング作業も自動化し、業務の効率化に成功しました。
ツインピックは高層棚コンテナ自動搬送ロボットと、低層棚自動搬送ロボットの2種類のロボットを同時に制御し、人の手の届かない高い棚にも自動で移動し、瞬時に入庫することが可能です。人の手による入庫作業では40分かかっていたところ、ツインピックでは10分で完了し、ラベルレスで作業可能なため省人化、省資源化も実現しました。
\稼働中のツインピックを実際にご覧いただける倉庫見学会を開催中!/
ユアサ商事様での事例は、こちらの記事でご紹介しておりますので参考にしてください。
自動倉庫を活用することで入庫作業のスムーズ化を実現

そこで、センターの効率化を目指すために、東日本物流センターでは縦型リフト式自動倉庫「Kardex Shuttle(カーデックス シャトル)」を導入しました。この自動倉庫を導入することで、通常のラック保管と比較して保管効率が約250%改善するほか、入庫、ピッキング、出庫などの倉庫内作業が大幅にスムーズ化し、生産性が向上しています。
入庫作業では、作業者の手元で棚が動いて入庫できるため、作業者の負担が大幅に軽減。入庫精度も向上し、物流の効率化に貢献しています。
このようにプラス ロジスティクスでは、荷主企業が扱う商品の特性に合わせた物流ロボットやマテハン機器を選択し、ベストなオペレーションを提案することが可能です。無駄を省いた最新の物流プロセスをカスタマイズいたします。
NaITO様での事例は、こちらの記事でご紹介しておりますので参考にしてください。
入庫業務の効率化には物流専門のプロへご相談を
入庫業務は、物流の中でも重要な工程です。入庫が正確に行われることで、その後の工程でのミスが抑制でき、エンドユーザーからの評価が高まります。正確性を高めるためにはさまざまな方法がありますが、中でもWMSやロボットなどのシステムを導入することで、運用はスムーズになるでしょう。
自社で物流のすべてを行うのは、リソースの圧迫につながります。物流のプロにアウトソーシングすれば、物流を一括で任せることができ、手間をかけずに最適な物流システムが実現可能です。
プラス ロジスティクスグループでは、それぞれのお客様の事情に合わせた物流システムをカスタマイズし、ご提案します。入庫業務の効率化を目指すお客様は、ぜひプラスロジスティクスグループにお問い合わせください。